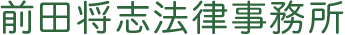相続の解決事例-相続開始から8年後に相続放棄申述が受理された事例-
※依頼者の方から書面による承諾を得て、解決事例を掲載しています。
(1)事例の概要
被相続人が平成29年に亡くなられたところ、令和7年に被相続人に関する金銭請求があり、それを知って、依頼者が相続放棄を進めた事例です。
(2)解決内容
最高裁昭和59年4月27日判決等を引用の上、諸事情を踏まえれば、民法915条1項所定の熟慮期間は請求があったことを知ってから起算されると主張しました。
その結果、裁判所に相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理証明書が交付されました。
(3)所感
民法915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。
上記を素直に読めば、相続の開始があったことを知ったとき、言い換えれば、被相続人が亡くなり、自身が相続人であることを知ったときから3か月以内に相続放棄をする必要があると解されます。
しかし、最高裁昭和59年4月27日判決は、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に相続放棄等をしなかったとしても、それが相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時、または、通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であると判示しました。
ここでいう相当な理由の有無は、これまでの裁判例等を踏まえて、具体的事案ごとに判断されます。相続放棄を検討されている方がいらっしゃれば、まずは法律専門家に相談することが大切といえそうです。